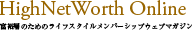富裕層向け商品・サービスの研究開発成功のポイントは定期的・継続的に富裕層の意見を取り入れる「ハイネットワースラボ」
多くの企業が新しい商品、サービスを生み出すために日々研究開発をおこなっている。
日本で最も研究開発費が多いのは、日本一の自動車メーカー「トヨタ自動車」だ。
今回は、そのトヨタ自動車の研究開発の極意と、本誌が実施したアンケート結果をもとに、富裕層顧客向けの商品、サービスを生み出すための最大にして唯一の方法論、「ハイネットワースラボ」について改めて考察する。
わからないから失敗するという研究開発のシンプルな真理
日々多くの企業が新しい商品、サービスを生み出すために研究開発をおこなっている。
当然、一般的な顧客をターゲットとしたものもあれば、富裕層顧客をターゲットとしたものもある。
当社では、今回富裕層向け商品、サービスの研究開発に関して緊急アンケートを実施し、いくつかの貴重な意見が得られた。
たとえば、富裕層向け商品、サービスの研究開発があまりうまくいっていないと回答したある企業は、その理由として「富裕層のことがよくわからないため。富裕層ビジネスに精通した人材が社内にいないため」と答えている。
また、「単にリサーチするだけでは、富裕層が何を良いと感じるか、どのようなことに共感するかなどを掴むことが難しい」とも感じているようだ。
富裕層をターゲットとした商品、サービスを開発したいのに、富裕層のことがよくわからないままではなかなかうまくいかないのも当然だろう。
富裕層向け商品、サービスの開発を成功させる鍵は、究極的には1つの方法論に行き着くというのが、これまでと変わらない本誌の意見だ。
定期的、継続的に富裕層の意見を取り入れ、それを正しく分析し、その結果を踏まえて開発を進めていく方法で、本誌の「ハイネットワースラボ」という商品がこれにあたる。
まさに、先に挙げた課題をそのまま解決するものだ。
トヨタの研究開発の要「主査制度」
実は「ハイネットワースラボ」と非常に近い考え方に基づいて研究開発をおこなっているのがトヨタ自動車だ。
トヨタ自動車の研究開発の特徴は「主査」という制度だ。
もともとは航空機の製造現場で取り入れられていた制度で、1953年に当時常務だった豊田英二氏がトヨタで始めたものが今も続いているというわけだ。
主査とは市場、顧客・非顧客、競合、技術、原価など、設計や製造の技術、ビジネス全体をに精通している人物のことで、主査が司令塔となって商品のコンセプト、性能、ターゲット、価格などの開発設計情報が決められる。
例えばクラウンの主査であれば、クラウンに関する全ての最終決定権を有していることを意味する。
つまりこの体制の下で作られる開発設計情報には、単にどの素材、部品を使ってどのような車を作るかという情報だけでなく、原価をいくらに抑えて、このようなターゲットにいくらで売るという情報まで含まれている。
言い換えれば、売れる商品を作るための情報ということだ。
トヨタと比較して、逆に「作ったものを売っている」と言われるのが日本の半導体メーカーだ。
ご存じの通り、エルピーダが経営破綻し、ルネサスも長い間赤字が続いていたなど、日本の半導体業界は苦しい状況だ。
この要因のひとつが、性能や品質を最優先するあまり、コスト意識が低かったことだと言われている。
設計や製造の技術については精通しているが、コスト意識や市場動向の把握など、ビジネス全体については必ずしも熟知していたわけではない。
つまり、日本の半導体メーカーにはトヨタの研究開発における主査の役割を担う人材がいないため、「売れるものを作る」プロセスを構築できなかったということだ。
対照的にアメリカのインテルはトヨタの研究開発や生産方式を学び、自社にも主査制度を取り入れているそうだ。
富裕層向け商品・サービスの研究開発に必要な富裕層ビジネス版「主査」
冒頭で紹介したアンケートの回答にもあるように、富裕層向け商品、サービスの開発も同じような環境にあると本誌は考えている。
主査の役割、つまり富裕層ビジネスに精通した人材が研究開発に関わることができていないために、「作ったものを売る」ことになってしまっているケースが少なくない。
冒頭の企業では富裕層リサーチを実施しているが、富裕層ビジネスの知識やノウハウがないと、そもそも調査設計が間違っている可能性も十分に考えられる。
それどころか、実際にはリサーチ自体実施するのが困難なケースのほうが多いのではないだろうか。
中期経営計画に富裕層戦略を盛り込む日本企業が増えてきているが、「富裕層に売れるものを作る」ためには、トヨタの例からもわかる通り、富裕層ビジネスに精通した人材が研究開発に携わることが最大のポイントであり、同時に唯一の方法だというのが本誌の結論だ。